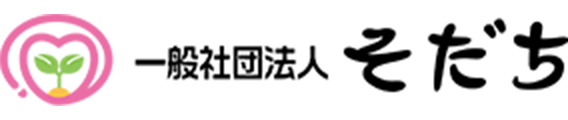ブログ
なぜ発達障害を「神経発達症」というの?
この秋は
発達障害(神経発達症)セミナーを行います。
こんにちは!
子どもの育ちを応援します!
一般社団法人そだち 内田淑佳(うちだよしか)です。
「発達障害」という名称から
「神経発達症」という表記に変更があったのが
2022年「DSM-5-TR」
(邦訳は2023年)
「DSM」とは
米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」
「-5-TR」とは
第5版のテキストリビジョン(本文改定)のことです。
多くの病気(疾患)が
~障害 という言い方から
~症 に変更されたことが
大きな特徴です。
なぜ、このような変更が行われたのか。
これは
時代の変化による
環境の変化を捉えたものであり
病気への理解、
認知を高めるという意図と
精神の疾患は
症状のあるご本人の
視点に立ち
考えられるものでなければならない
ということ。
その症状は
一人一人
違うものであり
そこにこそ
フォーカスすべきであると
私は考えます。
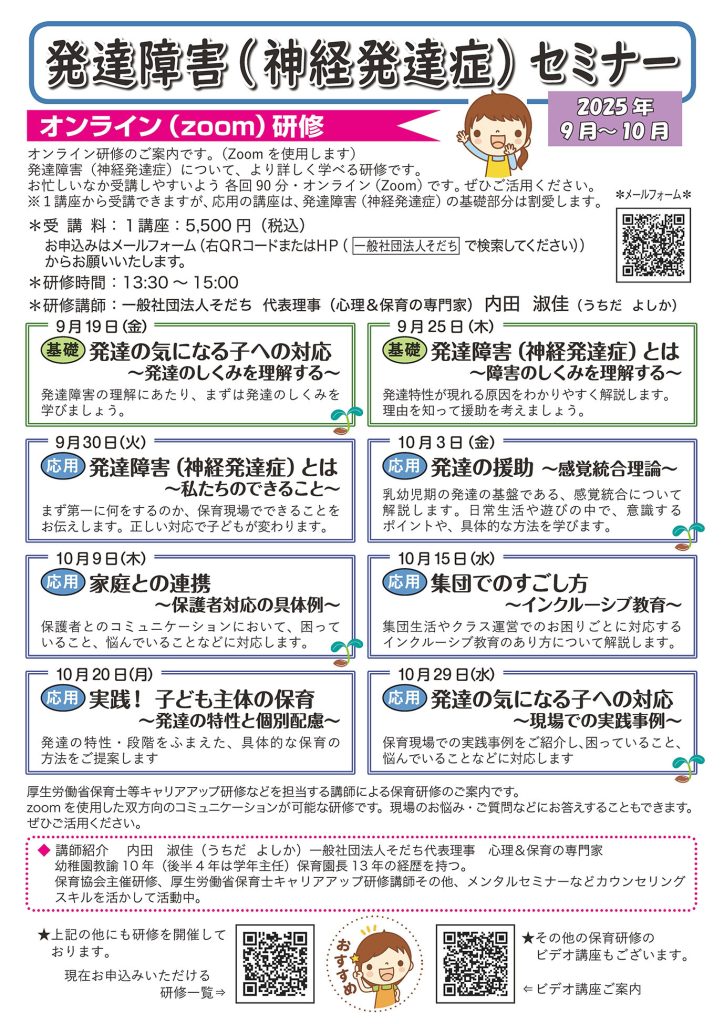
この秋は
発達障害(神経発達症)セミナーを行います。
基礎の2講座で
発達障害(神経発達症)を
しっかりと理解できる内容となっております。
基礎の1
「発達の気になる子への対応~発達の仕組みを理解する~」
この講座で
「発達」というもの
そのものを理解します。
「発達」が理解できてはじめて
「発達の障害」がわかるというもの。
子どもが
どのように発達をしていくのかを知ることで
発達の気になる子への対応が
わかるようになります。
そして
基礎の2
「発達障害(神経発達症)とは~障害の仕組みを理解する~」
ここで
さきほどの「DSM-5-TR」の話をします。
発達障害とは
子どもの発達=脳神経の発達
のところに
何らかの問題がおきている状態をいいます。
そして
ここでは「スペクトラム」の解説をします。
どの病気もすべて
「スペクトラム」であり
私たち人間はみな
「スペクトラム」である。
他におススメは
「発達の援助~感覚統合理論~」です。
実際にこの「感覚統合理論」で
子どもさんへのアプローチ方法が
わかります。
現場で
たくさんの子どもさんが
しっかり伸びています。
そして
最も大切なことは
「発達障害(神経発達症)とは~私たちのできること~」
の講座の中でお話しています。
この講座では
発達障害(神経発達症)の当事者の
みなさまが
自分の人生を振り返って語っておられることを
参考に
「人生にとって大切なこと」をお話します。
ズバリ言うと
二次障害についてです。
発達障害(神経発達症)のあることで
起きてくる
二次障害を予防したい。
それが
乳幼児期の子どもたちに関わる
私たちにできること
いえ、
するべきこと
だと考えるからです。
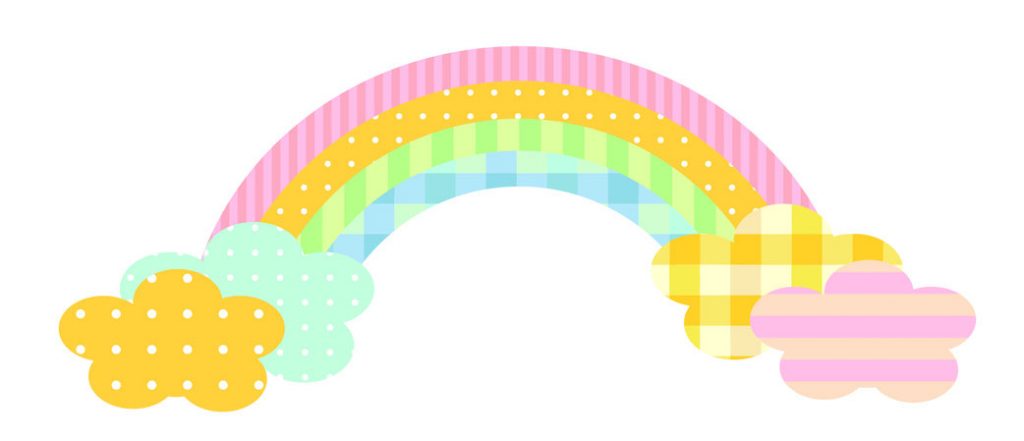 メンバー限定♡オンラインサロン
メンバー限定♡オンラインサロン
♡ご案内ページはコチラ♡
※現在お申込み頂ける研修・講座はコチラから
※保育士のためのコミュニケーション講座
心理学・対人スキル・人材育成
(少人数制で、リアルなお悩みを解決する講座です)
オンライン受講もできます!
詳細はコチラのページをご覧ください。
※子どもの発達心理アドバイザー養成講座
(子どもの発達心理、発達過程、発達障害を専門的に学ぶ講座です)
オンラインで個別受講もできます!
詳細はコチラのページをご覧ください。
一般社団法人そだち
代表&心理・保育研修講師
内田淑佳(うちだよしか)
個人セッションご案内はコチラ
Follow @UchidaYoshika
「一般社団法人そだち」公式LINE
悩みごと、相談などメッセージしてください!
発達障害(神経発達症)セミナーを行います。
こんにちは!
子どもの育ちを応援します!
一般社団法人そだち 内田淑佳(うちだよしか)です。
「発達障害」という名称から
「神経発達症」という表記に変更があったのが
2022年「DSM-5-TR」
(邦訳は2023年)
「DSM」とは
米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル」
「-5-TR」とは
第5版のテキストリビジョン(本文改定)のことです。
多くの病気(疾患)が
~障害 という言い方から
~症 に変更されたことが
大きな特徴です。
なぜ、このような変更が行われたのか。
これは
時代の変化による
環境の変化を捉えたものであり
病気への理解、
認知を高めるという意図と
精神の疾患は
症状のあるご本人の
視点に立ち
考えられるものでなければならない
ということ。
その症状は
一人一人
違うものであり
そこにこそ
フォーカスすべきであると
私は考えます。
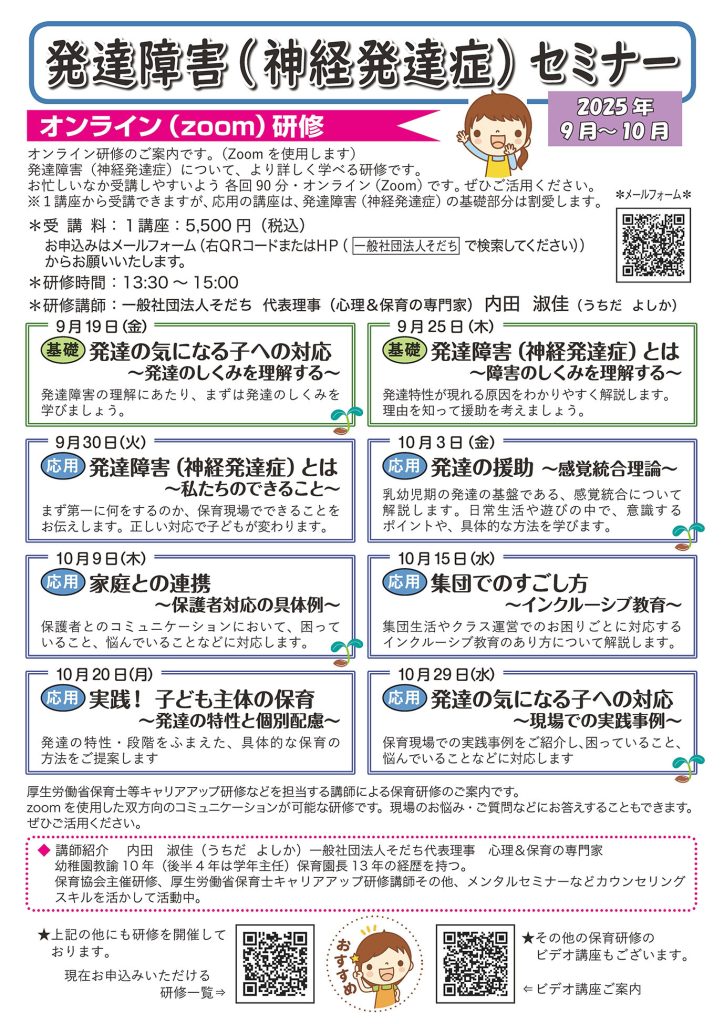
この秋は
発達障害(神経発達症)セミナーを行います。
基礎の2講座で
発達障害(神経発達症)を
しっかりと理解できる内容となっております。
基礎の1
「発達の気になる子への対応~発達の仕組みを理解する~」
この講座で
「発達」というもの
そのものを理解します。
「発達」が理解できてはじめて
「発達の障害」がわかるというもの。
子どもが
どのように発達をしていくのかを知ることで
発達の気になる子への対応が
わかるようになります。
そして
基礎の2
「発達障害(神経発達症)とは~障害の仕組みを理解する~」
ここで
さきほどの「DSM-5-TR」の話をします。
発達障害とは
子どもの発達=脳神経の発達
のところに
何らかの問題がおきている状態をいいます。
そして
ここでは「スペクトラム」の解説をします。
どの病気もすべて
「スペクトラム」であり
私たち人間はみな
「スペクトラム」である。
他におススメは
「発達の援助~感覚統合理論~」です。
実際にこの「感覚統合理論」で
子どもさんへのアプローチ方法が
わかります。
現場で
たくさんの子どもさんが
しっかり伸びています。
そして
最も大切なことは
「発達障害(神経発達症)とは~私たちのできること~」
の講座の中でお話しています。
この講座では
発達障害(神経発達症)の当事者の
みなさまが
自分の人生を振り返って語っておられることを
参考に
「人生にとって大切なこと」をお話します。
ズバリ言うと
二次障害についてです。
発達障害(神経発達症)のあることで
起きてくる
二次障害を予防したい。
それが
乳幼児期の子どもたちに関わる
私たちにできること
いえ、
するべきこと
だと考えるからです。
※オンライン(Zoom)です。
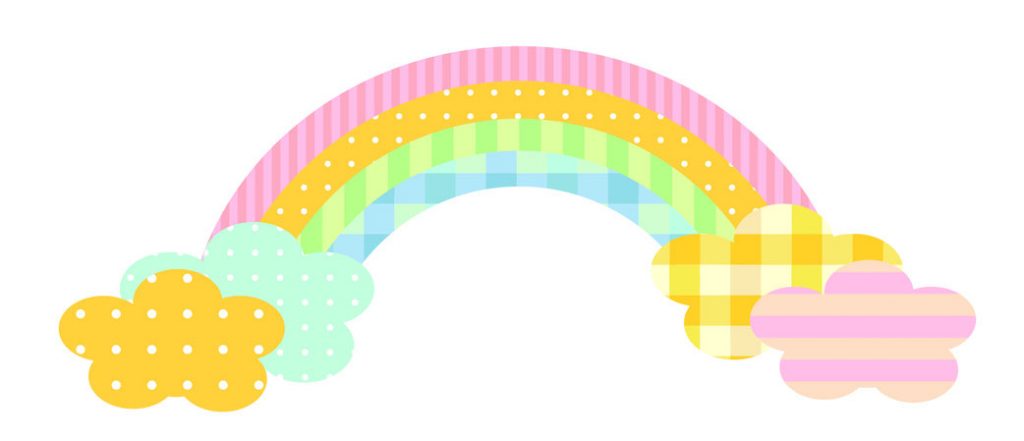 メンバー限定♡オンラインサロン
メンバー限定♡オンラインサロン♡ご案内ページはコチラ♡
※現在お申込み頂ける研修・講座はコチラから
※保育士のためのコミュニケーション講座
心理学・対人スキル・人材育成
(少人数制で、リアルなお悩みを解決する講座です)
オンライン受講もできます!
詳細はコチラのページをご覧ください。
※子どもの発達心理アドバイザー養成講座
(子どもの発達心理、発達過程、発達障害を専門的に学ぶ講座です)
オンラインで個別受講もできます!
詳細はコチラのページをご覧ください。
一般社団法人そだち
代表&心理・保育研修講師
内田淑佳(うちだよしか)
個人セッションご案内はコチラ
Follow @UchidaYoshika
「一般社団法人そだち」公式LINE
悩みごと、相談などメッセージしてください!
New Article
Archive
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年2月
- 2017年1月
- 2016年2月
- 2014年4月